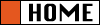揤慠愼椏婄椏夛媍丂婡娭帍
嵟廔峏怴擔丗2025.9.1
丂揤慠愼椏婄椏夛媍偱偼丄婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘乿乮俬俽俽俶丗2432-3136乯傪敪峴偟偰偒偰偄傑偡丅2018擭搙斉傑偱偼枅擭敪峴偱偒偰偄傑偟偨偑丄偦傟埲崀敪峴偑懾偭偰偄傑偡丅2018擭搙斉傑偱偼丄嶜巕懱偲偟偰嶌惉偟偰偄傑偟偨偑丄2023擭搙斉偐傜偼丄揹巕壔偡傞偲偲傕偵丄僶僢僋僫儞僶乕傕PDF僼傽僀儖偲偟偰斝晍偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅
丂2025擭9寧1擔偵丄婡娭帍2025乮斝晍壙奿丗1000墌乯傪敪峴偟傑偟偨偺偱偍抦傜偣偟傑偡丅偛婓朷偺曽偼丄偙偪傜偺怽崬僼僅乕儉偐傜偍怽偟崬傒壓偝偄丅僶僢僋僫儞僶乕偵偮偄偰傕丄摨偠怽崬僼僅乕儉偐傜偍怽偟崬傒壓偝偄丅嵟怴斉丄僶僢僋僫儞僶乕偲傕丄揹巕斉偼奺崋1,000墌偱偺斝晍偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
仸2004丄2005丄2007丄2011丄2012丄2017丄2018偼丄嶜巕懱偺巆晹偑庒姳偁傝傑偡丅嶜巕懱傪偛婓朷偺応崌偼丄3000墌偱斝晍抳偟傑偡偺偱丄帠柋嬊偵丄儊乕儖偱偛憡択偔偩偝偄丅
丂帠柋嬊丂e-mail
仧奺崋偺撪梕偼丄偙偺儁乕僕偺乽栚師堦棗乿傪偛棗壓偝偄丅
仧埲壓偺奺崋偺僋儕僢僋偡傞偲僷僗儚乕僪偺擖椡夋柺偑丄僨傿僗僾儗僀偺嵍忋側偳偵尰傟傑偡丅
仧僷僗儚乕僪偼丄怽崬僼僅乕儉偵傛傝丄帠柋嬊偵峸撉怽崬傪偝傟丄峸撉椏傪擺擖偝傟偨曽偵e-mail偱楢棈偟傑偡丅
仧楢棈偝傟偨僷僗儚乕僪偼丄懠偺曽偵偼嫵偊側偄傛偆偵偍婅偄偟傑偡丅懠偺曽偼丄揤慠愼椏婄椏夛媍偲峸撉宊栺傪偟偰偄側偄偺偱丄峸撉幰偲揤慠愼椏婄椏夛媍偼晄棙塿傪旐傞亖堘斀峴堊偵側傝傑偡偺偱丄偔傟偖傟傕媂偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仧婡娭帍偼僟僂儞儘乕僪傕偱偒傑偡偑丄偦偺僼傽僀儖傪懠偺曽偵搉偡偙偲偑柍偄傛偆偵偍婅偄偟傑偡丅
仜婡娭帍2004丗2004擭12寧侾擔敪峴偺憂姧崋乮慡74儁乕僕乯
仜婡娭帍2005丗2005擭12寧9擔敪峴乮慡84儁乕僕乯
仜婡娭帍2006丗2007擭3寧28擔敪峴乮慡66儁乕僕乯
仜婡娭帍2007丗2008擭3寧26擔敪峴乮慡68儁乕僕乯
仜婡娭帍2008丗2009擭3寧26擔敪峴乮慡57儁乕僕乯(尨場晄柧側偺偱偡偑丄僼僅儞僩偑堎忢偵側傞偙偲偑偁傞偐傕偟傟傑偣傫丅撪梕偺攃埇偼壜擻偱偡丅乯
仜婡娭帍2009丗2010擭4寧30擔敪峴乮慡45儁乕僕乯
仜婡娭帍2010丗2011擭10寧20擔敪峴乮慡48儁乕僕乯
仜婡娭帍2011丗2012擭4寧20擔敪峴乮慡38儁乕僕乯
仜婡娭帍2012丗2013擭4寧15擔敪峴乮慡52儁乕僕)
仜婡娭帍2013丗2014擭4寧1擔敪峴乮慡66儁乕僕乯
仜婡娭帍2014丗2015擭4寧1擔敪峴乮慡56儁乕僕乯
仜婡娭帍2015丗2016擭5寧20擔敪峴乮慡44儁乕僕乯
仜婡娭帍2016丗2017擭7寧11擔敪峴乮慡42儁乕僕乯
仜婡娭帍2017丗2018擭8寧20擔敪峴乮慡54儁乕僕乯
仜婡娭帍2018丗2019擭11寧敪峴乮慡40儁乕僕乯
仜婡娭帍2023丗2023擭8寧25擔敪峴乮慡60儁乕僕乯
仜婡娭帍2025丗2025擭9寧1擔敪峴乮慡142儁乕僕乯
 婡娭帍偺峔惉偲幏昅梫椞
婡娭帍偺峔惉偲幏昅梫椞
婡娭帍乽揤慠偺怓乿栚師堦棗
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2025乿栚師
姫 摢 尵丂枹棃傊偺怴偨側媄弍偲揱摑亙晲屔愳彈巕戝妛柤梍嫵庼丂媿揷丂抭亜
尋媶曬崘丂僔僐儞(巼崻)偺幚梡惗嶻偵岦偗偨儉儔僒僉嵧攟(Lithospermum erythrorhizon):杒奀摴摉暿挰偱偺庢傝慻傒乮怉暔壢妛偵傛傞帩懕壜擻側抧媴娐嫬曐慡幮夛偺峔抸乯亙杒奀摴堛椕戝妛丒栻妛晹丂崅忋攏
婓廳亜
尋媶曬崘丂巼崻愼傔偺愼怓壏搙偵偮偄偰偺尋媶挷嵏 乣巼崻偺崅壏愼怓偺壜擻惈傪扵傞乣亙揤慠怓岺朳tezomeya 惵栘 惓柧亜
尋媶曬崘丂堬忛導忢棨懢揷巗偵偍偗傞帺惗僯儂儞傾僇僱偺嵦庢偲愼怓帋尡亙惣壀桰惗亜
尋媶曬崘丂搶峀搰巗埨廻(偁偡偐)偵帺惗偡傞僯儂儞傾僇僱惗崻偲偦偺搚抧偺桸悈偲悈摴悈傪巊梡偟偨帋尡愼怓亙洀悈摪僐儗僋僔儑儞 悈栰宐巕丄恴朘桾旤亜
尋媶曬崘丂奺抧偵帺惗丄嵧攟偟偰偄傞僯儂儞傾僇僱偺惗堢娐嫬丄怓慺偺拪弌曽朄丂攠愼嵻偲慇堐丄崻偺検偺専摙丄愼怓惈偲應怓僨乕僞偺曬崘亅侾亙廰揷榓旤丄暉塱宐巕丄惣懞偟偺傇丄戝旤桼婭丄栴弌彯巕丄嵅摗宧巕丄枛淎媣旤巕丄搈栰僕乕僫丄壎懞斾楥巕丄巵揷崃媩丄妏庻巕亜
尋媶曬崘丂朇娵栘偺幚偵傛傞棔愼幚尡曬崘偲僩儗僯傾壴曎偺椢怓愼傔亙嫗搒巗棫寍弍戝妛戝妛堾旤弍尋媶壢岺寍愱峌愼怐 旤攏杸栯亜
尋媶曬崘丂揤慠愼椏傪梡偄偨怐暔惂嶌 捽怐拝暔乽嗤乆棎乿亙愼怐嶌壠 懌棫 恀幚亜
尋媶曬崘丂棔偺尰応偐傜亅4庬椶偺棔怉暔偲偦偺愼椏丄棔敪峺塼偺尋媶亙杒偺棔岺朳丂妏庻巕亜
榑丂丂愢丂旂丒妚丒梃偲桠偟朄亙棶媴戝妛柤梍嫵庼 曅壀丂弤亜
幚慔曬崘丂奰廰傪梡偄偨僾儕儞僩僥僉僗僞僀儖亙嫗搒巗棫寍弍戝妛 嶳拞 嵤亜
幚慔曬崘丂乽巼崻乿屆戙偺巼愼怓嵞尰幚尡曬崘亙戝庤慜戝妛嫵庼 偄傑傆偔 傆傒傛亜
幚慔曬崘丂僯儂儞傾僇僱惗崻帋尡愼亅嵧攟偐傜愼怓傑偱亅亙搈栰僕乕僫亜
揥帵夝愢 悘昅丂挆摏昤搾忋偘丒幦挔丒鍭屮偐傜師悽戙傊偺暥壔宲彸傪峫偊傞亙洂悈摪僐儗僋僔儑儞丂悈栰宐巕亜
峴帠儗億乕僩丂娭惣枩攷EXPO儊僢僙 WASSE擔杮崙嵺寍弍嵳 弌昳媦傃儚乕僋僔儑僢僾曬崘亙戝庤慜戝妛嫵庼 偄傑傆偔 傆傒傛亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞18夞戝夛丂奣梫
揥棗夛忣曬丂乽儌僲偵妛傃丄傕偺傪偮側偖亅悈丒搚丒拵丒憪栘丒廱栄丒愼椏丒晍側偳亅乿揥偵婑偣偰
怴摴峅擵偝傫傪幟傇
晅丂丂榐丂夛懃丄塣塩嵶懃
晅丂丂榐丂杮帍偺奣梫丄曇廤屻婰
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2023乿栚師
姫 摢 尵丂乽揤慠偺怓乿偺揹巕斉偱偺敪峴偵偁偨偭偰亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
尋媶曬崘丂掚偺壴偨偪偺愼傔丂錕錘偺拪弌塼偲對晍偺怓亙搈栰僕乕僫亜
尋媶曬崘丂鉘偺僨僕僞儖傾乕僇僀僽峔抸偵岦偗偨庢傝慻傒偲搶撿傾僕傾偺庡梫側鉘偺尰懚忬嫷偵娭偡傞曬崘亙峕岥 媣旤丄恵摗 棾擵夘丄晍巤 寬屷丄幁栰 梇堦丄媣曐 桾婱亜
尋媶曬崘丂鉘偺媄朄暘椶亅屇徧丗媄朄丒暘晍傪拞怱偵亅亙曅壀丂弤亜
尋媶曬崘丂栰憪丄栰嵷偐傜偺婄椏嶌傝偲梤栄偱偺帋偟愼傔 2022擭偺儚乕僋偐傜亙戝孎 桼棛峕亜
尋媶曬崘丂俆庬椶偺棔愼椏敪峺寶偵傛傞梤栄愼 俀乣偡偔傕棔丒僂僅乕僪偡偔傕偲捑揵棔偺敪峺塼偵偮偄偰亙愼怐壠丄杒偺棔愼怐岺朳丂妏丂庻巕亜
幚慔曬崘丂僂儊僲僉僑働偺敪峺愼丗拪弌偲愼怓丄嬨廈偱嵦庢偟偨愼椏怉暔偲愼傔怓慔曬崘亙捗壆嶈棔偄傠偺夛丂廰揷 榓旤亜
幚慔曬崘丂恀柸庤朼巺偺捴梩奃攠愼巼崻愼 10擭偺愼傔偺婰榐偲愼巺乣幦捽懷偲愼恀柸庤朼巺帒椏亙巵揷 崃媩亜
幚慔曬崘丂揤慠愼椏偲婄椏傪梡偄偨宆愼偺幚尡偲惂嶌亙栴弌 彯巕亜
夝丂丂愢丂灨巻(搚嵅灨)亙幁晘惢巻姅幃夛幮丄戙昞庢掲栶丂鸐揷 攷惓亜
悘丂丂昅丂棔傪抁壧偵塺傫偱亙垻晹 徍巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞16夞戝夛傪廔偊偰亙曅壀丂弤亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞16夞戝夛in扥攇偵嶲壛偟偰亙尦扥攇巗抧堟偍偙偟嫤椡戉乮扥攇晍乯 惣旜丂恀悷亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞17夞戝夛in崅抦丂奣梫亙媿揷丂抭亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2018乿栚師
姫 摢 尵丂乽揤慠愼椏婄椏夛媍 戞15夞戝夛傪廔偊偰乿亙塅搒媨戝妛嫵堢妛晹丂嵅乆栘丂榓栫亜
尋媶曬崘丂乽係庬椶偺棔愼椏敪峺寶偵傛傞梤栄愼侾乿亙杒偺棔愼怐岺朳丂丂妏丂庻巕亜
幚慔曬崘丂乽宱鉘偢傜偟媄朄偺嶌昳偲丄偦偺惂嶌偱偺棔媦傃愼椏偵偮偄偰乿亙峀搰巗棫戝妛寍弍妛尋媶壢 攷巑屻婜壽掱3擭 媣曐揷 姲巕亜
幚慔曬崘丂乽棔愼屆晍-懛懙偊丒鍭屮偲屄恖廚廤屆晍偺尰忬偲壽戣偵偮偄偰乿亙洂悈摪僐儗僋僔儑儞丂悈栰丂宐巕亜
幚慔曬崘丂乽戞37夞楌巎偲峫屆妛偵偍偗傞愼椏夛媍乿亙杒偺棔愼怐岺朳丂丂妏丂庻巕亜
峴帠儗億乕僩丂乽揤慠愼椏婄椏夛媍戞15夞戝夛奣梫乿亙塅搒媨戝妛嫵堢妛晹丂嵅乆栘丂榓栫亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2017乿栚師
姫 摢 尵丂乽揤慠愼椏婄椏夛媍 戞14夞戝夛傪廔偊偰乿亙捗壆嶈棔偄傠偺夛丂戙昞丂廰揷丂榓旤亜
尋媶曬崘丂乽儉儔僒僉偺摏嵧攟偵娭偡傞尋媶侾乿亙怴擔杮惢栻姅幃夛幮丂枛壀丂徍愰亜
尋媶曬崘丂乽鉘栦條偺扨埵暘椶偵娭偡傞堦峫嶡乿
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亙嬨廈戝妛帩懕壜擻側幮夛偺偨傔偺寛抐壢妛僙儞僞乕丂峕岥丂媣旤
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬨廈戝妛戝妛堾僔僗僥儉惗柦壢妛晎丂媣曐丂桾婱
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬨廈戝妛戝妛堾僔僗僥儉惗柦壢妛晎丂恵摗丂棾擵夘
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬨廈戝妛帩懕壜擻側幮夛偺偨傔偺寛抐壢妛僙儞僞乕丂晍巤丂寬屷
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搶嫗戝妛戝妛堾恖暥幮夛宯尋媶壢丂壀杮丂恀桽巕亜
尋媶曬崘丂乽棔敪峺寶偵揧壛偡傞梴暘丄娗棟壏搙偲pH偵偮偄偰乿亙杒偺棔愼怐岺朳丂妏庻巕亜
峴帠儗億乕僩丂乽揤慠愼椏婄椏夛媍戞14夞戝夛奣梫丄敪昞幰偺墶婄丄帒椏丒嶌昳揥帵乿
峴帠儗億乕僩丂乽暉壀戝夛丂愼怓幚廗乽嬨廈偺愼椏怉暔偱愼傔傞乿儗億乕僩亙捗壆嶈棔偄傠偺夛亜
悘丂昅丂丂丂乽捗壆嶈傊乿亙巵揷丂崃媩亜
峴帠儗億乕僩丂乽113夞栚偺彫偝側彫偝側抋惗嵳乽鉘偺壴傪嶇偐偣傑偟傚偆乣徏巬嬍婰偺悽奅乿亙廰揷榓旤丄幠揷撧弿旤丄恅嬇巕丄挿嶈彯旤亜
徯夘幨恀丂丂丂乽杒嬨廈暯旜戜偺儉儔僒僉乿丂
夛丂崘丂丂丂丂揤慠愼椏婄椏夛媍2018撊栘戝夛奐嵜偺偛埬撪丂丂丂丂丂丂丂
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2016乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍 戞13夞戝夛傪廔偊偰亙揤慠愼椏婄椏夛媍丂暃夛挿丂曅壀丂弤亜
尋媶曬崘丂揤慠偺棔偲旝惗暔丄偦偟偰恖亙僌儕乕儞丒僾儘僟僋僣丒儔儃儔僩儕乕丂忢斦丂朙丄杒偺棔愼怐岺朳丂妏庻巕丄傾僕傾岺壢戝妛堾丂Athapol Noomhorm丄壂撽導岺嬈媄弍僙儞僞乕丂悽壝椙丂岹搇亜
尋媶曬崘丂撿僼儔儞僗丄僇儞僽僱丒僔儏儖丒儖丒僜儖偺棔乽僷僗僥儖乿傪巺岥偵亙棶媴戝妛柤梍嫵庼丒棶媴愼怐暥壔尋媶強庡嵣丂曅壀丂弤亜
尋媶曬崘丂僂僅乕僪偺棔寶偰偲僀儞僪棔偲偺妱寶偰乣塼偺pH偲壏搙丄阰偲僀儞僕僑偺検偺専摙乣亙杒偺棔愼怐岺朳丂妏庻巕亜
尋媶曬崘丂擔杮偺俆庬椶偺棔怉暔偵傛傞愼椏嶌傝偲偦偺棔寶偰亙杒偺棔愼怐岺朳丂妏庻巕亜
尋媶曬崘丂媀楃晍僌儕儞僔儞偵偍偗傞愼怓朄偺埵抲偯偗亙僀儞僪僱僔傾崙棫寍弍戝妛媞堳嫵桜丒愼怐壠丂嶅尨 栁旤亜
婭丂丂峴丂丂嶳宍丂峠壴婭峴亙杒嶈丂栁庽亜
婭丂丂峴丂丂INTERNATIONAL FESTIVAL OF PLANTS, ECOLOGY AND COLOURS乣儅僟僈僗僇儖偱偺崙嵺夛媍曬崘乣亙妏丂庻巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞14夞戝夛丂奣梫
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2015乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞戞12夞戝夛乮搶嫗戝夛乯傪廔偊偰亙(姅)戝惉僐乕億儗乕僔儑儞丂捛暘晀彶亜
尋媶曬崘丂攄杹嶻僗僋儌傪梡偄偨棔愼傔塼偺旝惗暔亙僌儕乕儞丒僾儘僟僋僣丒儔儃儔僩儕乕丂忢斦丂朙丄壂撽導岺嬈媄弍僙儞僞乕丂悽壝椙丂岹搇亜
尋媶曬崘丂僂僅乕僪偺惗梩愼傔偵娭偡傞堦峫嶡亙塅搒媨戝妛嫵堢妛晹 嵅乆栘榓栫丄摗楺桭旤亜
尋媶曬崘丂抧堟偱堎側傞僀儞僪棔惢憿偲棔寶偰偺斾妑乣嵽椏偐傜傒傞惢棔偲娨尦曽朄乣亙愼怐壠丂妏丂庻巕丄愼怓壠丒壒妝壠丂郪栰丂岶亜
幚慔曬崘丂19擭慜偺偡偔傕棔偵傛傞奃廯敪峺寶偰幚慔曬崘亙旽愳丂弤巕亜
幚慔曬崘丂偡偔傕棔偲棶媴棔偺棔寶偰亙傾乕僥傿僗僩丂惎崌丂旤榓亜
榑丂丂愢丂挆杻悈怓抧攇摢婂峠梩柾條峠宆偺悽奅亙棶媴戝妛柤梍嫵庼丒棶媴愼怐暥壔尋媶強庡嵣丂曅壀丂弤亜
夝丂丂愢丂僽乕僞儞崙僥傿儞僾乕巗撪偺愼怓儚乕僋僔儑僢僾偵嶲壛偟偰亙棶媴戝妛柤梍嫵庼丒棶媴愼怐暥壔尋媶強庡嵣丂曅壀丂弤亜
婭丂丂峴丂帺慠偲偺挷榓偺拞偱惗傑傟傞怓亙傾乕僥傿僗僩丂惎崌丂旤榓亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞12夞戝夛丂奣梫
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2014乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞11夞戝夛傪廔偊偰亙旽愳丂弤巕亜
尋媶曬崘丂棔愼椏乮揇棔丄偡偔傕棔乯偲棔愼傔塼偺旝惗暔偺摿惈斾妑亙僌儕乕儞丒僾儘僟僋僣丒儔儃儔僩儕乕丂忢斦丂朙亜
尋媶曬崘丂僂僅乕僪偺惢棔丒棔寶偲嫵堢揑棙梡偵娭偡傞堦峫嶡亙塅搒媨戝妛嫵堢妛晹 嵅乆栘榓栫丒摗楺桭旤亜
尋媶曬崘丂屆戙巼(6,6'-僕僽儘儌僀儞僕僑)偺崌惉偲偦偺愼椏摿惈亙柧惎戝妛丒棟岺妛晹 郪揷 拤怣亜
尋媶曬崘丂壢妛偱昍夝偔屆戙偺愼怐媄弍偲偦偺嵽椏亙撧椙導棫妧尨峫屆妛尋媶強丂墱嶳惤媊亜
尋媶曬崘丂寴楽側棔愼偵偡傞偨傔偺嵽椏偺慖戰偲pH丒壏搙丒梴暘偺挷惍丂俀丂棶媴棔亙愼怐壠丂妏丂庻巕亜
幚慔曬崘丂宷偄偱備偔棔乣2011偐傜斾壝棶媴棔惢憿強偵偰丂棔偺嵧攟偐傜惢憿亙愼怓壠丄壒妝壠丂郪栰丂岶亜
榑丂丂愢丂棔偺柤徧偵偮偄偰亙棶媴戝妛柤梍嫵庼丒棶媴愼怐暥壔尋媶強庡嵣丂曅壀丂弤亜
悘丂丂昅丂帺慠偺怓偺椡亙巵揷丂崃媩亜
丂丂丂丂丂揤慠愼椏偵傛傞愼怓僒儞僾儖亙巵揷丂崃媩亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞11夞戝夛丂奣梫
丂丂丂丂丂丂丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞11夞戝夛傪廔偊偰亙拞搰丂捈巕亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2013乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞10夞戝夛傪廔偊偰亙洂悈摪僐儗僋僔儑儞庡嵣丂悈栰湪巕亜
尋媶曬崘丂惗暔懡條惈偺帇揰傪庢傝擖傟偨棔愼妶摦亙塅搒媨戝妛嫵堢妛晹丂嵅乆栘榓栫丄恄嶳峎堦乛幮夛暉巸朄恖梲岦 梲偩傑傝曐堢墍丂攼憅桪婫丄斞捤丂桪丄媑揷杻旤巕丄墶郪嵅榓巕丄扟揷晹捈巕丄戧揷壺擺巕丄杮揷丂愹亜
尋媶曬崘丂寴楽側棔愼偵偡傞偨傔偺嵽椏偺慖戰偲pH丒壏搙丒梴暘偺挷惍 侾丂偡偔傕棔亙妏丂庻巕乮愼怐壠乯亜
尋媶曬崘丂巼崻丒僒僼儔儞偵偍偗傞梤栄傊偺愼怓惈亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂巗愳嶇抭巕丄搒峛桼婭巕亜
尋媶曬崘丂僂儊僲僉僑働偵傛傞梤栄傊偺愼怓惈乣拪弌帪娫偲愼怓晍偺怓曄壔偺娭學乣亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂弔栘丂嵤丄搒峛桼婭巕亜
幚慔曬崘丂僂儊僲僉僑働丒巼崻丒僒僼儔儞愼怓梤栄僼僃儖僩儚乕僋僔儑僢僾奐嵜曬崘亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂巗愳嶇抭巕丄弔栘丂嵤丄挅栘旤桼婭丄郪悈壞昉丄椦丂桼壴丄嶰塝孿懢楴丄搒峛桼婭巕亜
榑丂丂愢丂棔偺敪揥亙棶媴戝妛柤梍嫵庼乮嫵堢乯丂曅壀丂弤亜
挷嵏曬崘丂擔杮偺奰廰偺尰嫷挷嵏亙崙棫戜榩岺寍尋媶敪揥拞怱丂暃庡擟丂捖丂懽徏丄崙棫戜榩岺寍尋媶敪揥拞怱丂暃尋媶堳丂墿丂廼恀丄峴惌堾擾埾橉椦嬈帋閯強丂彆棟尋媶堳丂幱丂栉晀巕亜
妶摦曬崘丂洂悈摪僐儗僋僔儑儞曬崘2013偲屆晍揥帵偁傟偙傟亙洂悈摪僐儗僋僔儑儞庡嵣丂妛寍堳丂悈栰宐巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞10夞戝夛丂奣梫亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
摿暿婑峞 丂棔偲垽偵摫偐傟偰亙棔愹娰 慜奯壚戙亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2012乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俋夞戝夛傪廔偊偰亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂搒峛 桼婭巕亜
尋媶曬崘丂戝暘導抾揷嶻僒僼儔儞愼傔偲搾偺壴攠愼巼崻愼傔偺嫵堢幚慔亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂杗揷 桭棟丄搒峛 桼婭巕亜
尋媶曬崘丂巼崻愼怓偵偍偗傞暿晎嶻搾偺壴攠愼擹搙偺愼怓惈傊偺塭嬁亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂媣曐嶳 幯婱丄搒峛 桼婭巕亜
尋媶曬崘丂妺偵傛傞對傊偺嬥懏攠愼愼怓亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂廫帪 埢壺丄搒峛 桼婭巕亜
幚慔曬崘丂妺偺惗梩丒僞儅僱僊偺奜旂偵傛傞搾偺壴攠愼愼怓 儚乕僋僔儑僢僾奐嵜曬崘亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂廫帪 埢壺丄媣曐嶳 幯婱丄杗揷 桭棟丄峚岥丂梲巕丄搒峛丂桼婭巕亜
夝丂丂愢丂僽乕僞儞偺愼怓亙儎僋儔儞僪乮僽乕僞儞備偭偔傝曌嫮夛乯庡嵣丂媣曐 弤巕亜
挷嵏曬崘丂僽乕僞儞丒塤撿徣偺暥壔偲愼怐亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂搒峛 桼婭巕丄偍拑偺悈彈巕戝妛丂挬斾撧 偼傞偐亜
夝丂丂愢丂搾偺壴偺尋媶乣搾偺壴偲僴僀僲僉偱儈儑僂僶儞傪偮偔傞乣亙尦暿晎戝妛抁婜戝妛晹丂嫵庼丂峆徏丂惒亜
妶摦曬崘丂洂悈摪僐儗僋僔儑儞妶摦曬崘亙洂悈摪僐儗僋僔儑儞庡嵣丂妛寍堳丂悈栰 宐巕 亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俋夞戝夛丂奣梫亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹旐暈妛尋媶幒丂媣曐嶳 幯婱丄晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
峴帠儗億乕僩丂戝暘戝夛偵嶲壛偟偰亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
夝丂丂愢丂婱晈恖偲堦妏廱偺僞僺僗儕偑擔杮偵傗偭偰偔傞亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2011乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俉夞戝夛傪廔偊偰亙岺朳棔壴丂桏丂氭巕亜
尋媶曬崘丂巼崻拪弌怓慺偵傛傞對傊偺愼怓壏搙埶懚惈媦傃搾偺壴攠愼岠壥亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂嵅摗埡嵒丄搒峛桼婭巕亜
尋媶曬崘丂柸丒杻偵懳偡傞僞儞僯儞巁丒恷巁傾儖儈僯僂儉偱偺巼崻偵傛傞愼怓亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂娵揷椱旤巕丄搒峛桼婭巕亜
尋媶曬崘丂揤慠愼椏偺拪弌偲暿晎嶻搾偺壴攠愼偵傛傞愼怓惈亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂杻惗枹棃丄搒峛桼婭巕亜
幚慔曬崘丂儀僢僾丒傾乕僩丒儅儞僗2011愼怓懱尡儚乕僋僔儑僢僾亙戝暘戝妛嫵堢暉巸壢妛晹丂杻惗枹棃丄嬥嶳桼棞崄丄嵅摗埡嵒丄娵揷椱旤巕丄搒峛桼婭巕亜
幚慔曬崘丂尨巒怐傝乽僇僢儁僞乿乣丂敧忎搰傛傝僕儍乕僕乕搰傊亙墿敧忎傔備岺朳丂嶳壓丂梍亜
尋媶曬崘丂條乆側揤慠攠愼嵻偵傛傞擔杮埄偺敪怓亙杒偺棔愼怐岺朳丄NPO朄恖傾乕僗僱僢僩儚乕僋丂妏丂庻巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俉夞戝夛丂奣梫亙岺朳棔壴丂桏丂氭巕亜
夝丂愢丂愼怓寴傠偆搙偵偮偄偰亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2010乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俈夞戝夛傪廔偊偰亙妏丂庻巕亜
幚慔曬崘丂揤慠愼椏偲婄椏傪巊偭偨宆愼偺尋媶偲嶌昳惂嶌亙栴弌 彯巕丄嵅摗 垷搒巕亜
幚慔曬崘丂僞儁僗僩儕乕嶌惉暔岅亙廰揷 榓旤亜
幚慔曬崘丂抾揷巗偺僒僼儔儞丄嵧攟偲僒僼儔儞愼傔亙巵揷 崃媩亜
尋媶曬崘丂戝暘導抾揷巗偵偍偗傞巼憪偺嵧攟偲巼崻偵傛傞攠愼愼怓亙搒峛 桼婭巕亜
幚慔曬崘丂澍棔丄擔杮埄丄儉儔僒僉偺嵧攟偲偦偺愼怓亙妏丂庻巕亜
尋媶曬崘丂儉儔僒僉偺惗崻偲姡憞崻傪巊偭偨愼怓偵偮偄偰亙妏丂庻巕亜
幚慔曬崘丂愒曚鉰捠乣愒曚鉰捠廋暅僾儘僕僃僋僩乣亙捛暘 晀彶亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俈夞戝夛丂奣梫亙媿揷丂抭亜
峴帠儗億乕僩丂ISEND 2011 Europe丂奣梫亙媿揷丂抭亜
峴帠儗億乕僩丂擔杮偺揤慠愼椏偲壠嶾對傪巊偭偨捽拝暔偺揥帵偲媄朄夝愢偲僨儌儞僗僩儗乕僔儑儞乮ISEND 2011乯亙妏丂庻巕亜
峴帠儗億乕僩丂ISEND 2011 Europe丂奣梫亙媿揷丂抭亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏僔儞億僕僂儉ISEND2011偲愼怐尋廋偵嶲壛偟偰亙嶳岥 壚撧亜
峴帠儗億乕僩丂崙嵺揤慠愼椏僔儞億僕僂儉偵嶲壛偟偰亙楅栘 晉旤巕亜
峴帠儗億乕僩丂ISEND2011偲尋廋椃峴偵嶲壛偟偰亙巵揷 崃媩亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2009乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俇夞戝夛傪廔偊偰亙帠柋嬊挿丂郪揷丂孿巌亜
幚慔曬崘丂棔偲嫟偵惗偒傞亙嶁搶丂枹棃亜
幚慔曬崘丂怉暔奊偺嬶偺僇儔乕僟僀儎儖亙壎懞丂斾楥巕亜
幚慔曬崘丂栻梡偲偟偰傕巊傢傟傞愼椏怉暔傪妛傫偱亙垻晹丂撝巕亜
幚慔曬崘丂僂僈儞僟偱偺妶摦偲愼怓亙娾嶳丂奊棟亜
幚慔曬崘丂柸偺愼丗壓抧嶌傝丂愭攠愼丂愼怓丂偦偟偰愻戵亙妏丂庻巕亜
幚慔曬崘丂捗壆嶈棔偄傠偺夛偺侾擭亙廰揷丂榓旤亜
幚慔曬崘丂儀儞僈儖抧曽偺揤慠愼椏傾乕僥傿僗僩亙忋尨丂庒嵷亜
婭丂丂峴丂儀僩僫儉擔婰亙嵅栰丂旤庽亜
夝丂丂愢丂揤慠愼椏偲鉘怐暔亙曅壀丂弤亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俇夞戝夛丂奣梫
峴帠儗億乕僩丂揤慠偺怓揥偲嫟摨嶌昳惂嶌儚乕僋僔儑僢僾2007-2009
峴帠儗億乕僩丂惗暔懡條惈偐傜傒偨帩懕壜擻側揤慠帒尮偲偟偰偺愼椏丒栻梡怉暔偲揤慠慇堐
亅庬偺懚懕偲恖娫偺惗嶻妶摦偺帩懕壜擻惈傪媮傔偰亅
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2008乿栚師
姫 摢 尵丂丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俆夞戝夛 in 杒奀摴亙杒偺棔岺朳庡嵣丂妏丂庻巕亜
夝丂丂 愢丂丂洀悈摪僐儗僋僔儑儞偵偮偄偰亙洀悈摪僐儗僋僔儑儞庡嵣丂悈栰湪巕亜
夝丂丂 愢丂丂僇僀僈儔儉僔桼棃偺儔僢僋愼椏偵偮偄偰亙偍拑偺悈彈巕戝妛戝妛堾丂搒峛桼婭巕亜
挷嵏曬崘丂丂僽乕僞儞偵偍偗傞儔僢僋愼椏偺埵抲偯偗偍傛傃惗嶻亙偍拑偺悈彈巕戝妛戝妛堾 搒峛桼婭巕亜
尋媶曬崘丂丂僽乕僞儞偵偍偗傞儔僢僋愼椏傪梡偄偨愼怓亙偍拑偺悈彈巕戝妛戝妛堾 搒峛桼婭巕亜
夝丂丂 愢丂丂椢搚偺婄椏偲偟偰偺惈幙亙搶嫗錣弍戝妛丂嵅摗墰堢亜
幚慔曬崘丂丂儉儔僒僉偺帺惗庬偺娤嶡偲曐慡丄嵧攟偲庬斝晍偺帋傒亙妏丂庻巕丄壀廧桼旤巕丄拞懞丂桾亜
幚慔曬崘丂丂嵧攟偟偨儉儔僒僉偲擔杮埄偱愼傔傞亙杒偺棔岺朳庡嵣丂妏丂庻巕亜
幚慔曬崘丂丂巐棻偺儉儔僒僉偺庬 亙乮嵿乯妎梍夛丂慇堐愼怓尋媶強丂榌丂丂愹亜
婭丂丂 峴丂丂娯崙偱偺揤慠愼椏偵娭偡傞僔儞億僕僂儉偵嶲壛偟偰亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俆夞戝夛丂奣梫
摉擔攝晍帒椏丂巼崻愼傔偺愼怓壔妛偲墳梡 亙乮嵿乯妎梍夛丂慇堐愼怓尋媶強丂榌丂丂愹亜
夝丂丂 愢丂丂丂婾巼丂偵偣傓傜偝偒亙棶媴戝妛丒嫵堢妛晹丂曅壀丂弤亜
峴帠儗億乕僩丂乽愼椏丒栻梡怉暔僼僅乕儔儉乿偵嶲壛偟偰亙栴弌彯巕亜
峴帠儗億乕僩丂2008愼椏丒栻梡怉暔僼僅乕儔儉儗億乕僩丂撿晹巼崻愼丒埄愼揥亙墱栰惷巕亜
峴帠儗億乕僩丂弶忋棨丏丏丏杒奀摴亙傾乕僗僱僢僩儚乕僋暉壀帠柋嬊丂廰揷榓旤亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠偺怓揥偲嫟摨嶌昳惂嶌儚乕僋僔儑僢僾
峴帠儗億乕僩丂悰徖扖晇丂曅壀弤丂恊巕揥亙偍拑偺悈彈巕戝妛戝妛堾 搒峛桼婭巕亜
幚慔曬崘丂丂撿晹儉儔僒僉曐懚夛偵偮偄偰 亙撿晹儉儔僒僉曐懚夛亜
幚慔曬崘丂丂撿晹儉儔僒僉曐懚夛丂2007-2008擭偺妶摦 亙撿晹儉儔僒僉曐懚夛亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2007乿栚師
姫 摢 尵丂丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞4夞戝夛 in搶嫗 傪廔偊偰丂亙揤慠愼椏婄椏夛媍丂搶嫗帠柋嬊丂郪揷丂孿巌亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞4夞戝夛in搶嫗丂奣梫丂亙彫椦丂榓巕亜
峴帠儗億乕僩丂塅搒媨儚乕僋僔儑僢僾偵嶲壛偟偰丂亙錗丂氭巕亜
峴帠儗億乕僩丂塅搒媨儚乕僋僔儑僢僾偵嶲壛偟偰丂亙(姅)戝惉僐乕億儗乕僔儑儞丂捛暘丂彯巕亜
峴帠儗億乕僩丂壓栰崙丒塿巕丂嵁壆偺俀侽侽擭丂嬨戙栚偺俆侽擭
丂丂亙榖偟庤丂愼怓岺朳丂擔壓揷嵁壆丂擔壓揷丂惓亜
丂丂亙暦偒庤丂揤慠愼椏婄椏夛媍丂彫椦丂榓巕亜
晅丂丂榐丂丂塅搒媨儚乕僋僔儑僢僾偺攝晍帒椏丂亙塅搒媨戝妛丂嵅乆栘丂榓栫亜
峴帠儗億乕僩丂敧忎搰尋廋僣傾乕偵嶲壛偟偰丂亙彫椦丂榓巕亜
峴帠儗億乕僩丂敧忎搰尋廋偵婑偣偰丂亙敧愮戙嫟惗夛 巺朼偓島巘丂擔栰丂徍巕亜
峴帠儗億乕僩丂敧忎搰尋廋偲搰僣傾乕偺姶憐丂亙偍拑偺悈彈巕戝妛戝妛堾丂搒峛丂桼婭巕亜
夝丂丂愢丂丂墿敧忎偺愼傔偲怐丂亙墿敧忎傔備岺朳丂嶳壓丂梍亜
幚慔曬崘丂丂巕偳傕偲揤慠偺怓丂亙NPO傾乕僗僱僢僩儚乕僋丂郪揷丂孿巌亜
幚慔曬崘丂丂棔偺壠偲捗壆嶈棔偄傠偺夛丂亙捗壆嶈棔偄傠偺夛丂廰揷丂榓旤亜
幚慔曬崘丂丂傾僇僱壢愼椏怉暔傪捛偄偐偗偰丂亙杒偺棔岺朳丒傾乕僗僱僢僩儚乕僋丂妏丂庻巕亜
夝丂丂愢丂丂壂撽偺墿怓愼椏偍傛傃婄椏丂亙棶媴戝妛丒嫵堢妛晹丂曅壀丂弤亜
朘 栤 婰丂丂僔儞億僕僂儉乽敧廳嶳偺棔乿乣栘棔偺偙傟偐傜乣偵嶲壛偟偰丂亙杒偺棔岺朳丒傾乕僗僱僢僩儚乕僋丂妏丂庻巕亜
夝丂丂愢丂丂僂僈儞僟偱偺愼怓丂亙惵擭奀奜嫤椡戉堳丂娾嶳丂奊棦亜
夝丂丂愢丂丂愼怓傪偡傞恖偺偨傔偺傗偝偟偄壔妛丂亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
晅丂丂榐丂丂夛懃丄塣塩嵶懃丄杮帍偺奣梫丄夛崘丂 56
僐 儔 儉丂GEIC丄墿敧忎偺惗嶻丄揱摑揑岺寍昳丄塱娪挔丄偐傜傫岺朳丄嶰師尦寀岝僗儁僋僩儖暘愅
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2006乿栚師
姫 摢 尵丂丂揤慠愼椏婄椏夛媍偺俁擭娫丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂媿揷丂抭亜
幚慔曬崘丂丂壛夑栰嵷 嬥帪憪偺摿惈偲愼怓丂亙愼傔岺朳朑墿丂錗丂氭巕亜
幚慔曬崘丂丂帺壠惢偡偔傕嶌傝丂亙墱栰丂惷巕亜
幚慔曬崘丂丂儁僢僩儃僩儖傪棙梡偟偨捑揵棔偺嶌傝曽丂亙棶媴戝妛丒嫵堢妛晹丂曅壀丂弤亜
尋媶曬崘丂丂棔偺惗梩偵傛傞愒巼怓愼傔奺庬庤朄偺摿挜偲幚梡惈丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂屆郷桾庽丄媿揷丂抭亜
尋媶曬崘丂丂庽栘 亅 怓偲壒丂愼怓偲妝婍偺椉曽偵桳梡側擬懷偺庽栘 亅慻惉偲栘偺怓偲壒嬁偺娭楢偐傜丂亙嫗搒晎棫戝妛擾妛晹丒攷巑尋媶堳 Iris BREMAUD亜
幚慔曬崘丂丂杒尷偺廘栘偲僋僒僊愼偺桳岠惈亅帺惗愼椏怉暔偺曐慡偲嵧攟丄棙梡偲晛媦妶摦丂亙杒偺棔岺朳丒傾乕僗僱僢僩儚乕僋丂妏丂庻巕亜
幚慔曬崘丂丂挰暲傒偵抔楘傪偐偗傞擔偲柌尒偰丏丏丏丂亙捗壆嶈棔偄傠偺夛丂廰揷丂榓旤亜
夝丂丂愢丂丂宆愼傔偵偍偗傞愼椏偲婄椏偺幚慔揑側巊偄暘偗丂亙岺朳 怸 庡嵣丂栴弌丂彯巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俁夞戝夛 in 嫗搒 奣梫丂亙婰榐丒曇廤丗媿揷丂抭亜
峴帠儗億乕僩丂嫗搒戝夛偺姶憐丂亙摽搰導丂媑揷丂堦巬亜
昡丂丂榑丂丂揤慠愼椏婄椏夛媍 in嫗搒偺姶憐乽怓偼扤偺傕偺丠乿丂亙擄攇嶻嬈(姅)丂擄攇丂淎惏亜
婭丂丂峴丂丂僀儞僪偱偺揤慠愼椏崙嵺夛媍丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂媿揷丂抭亜
婭丂丂峴丂丂夦偟偄壸暔偲偲傕偵椃偼巒傑偭偨 亙側偧傗偟偒庡嵣丂桳尦丂崅懢亜
婭丂丂峴丂丂僀僊儕僗丒僼儔儞僗偺愼怐偵娭偡傞攷暔娰偺徯夘丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂媿揷丂抭亜
婭丂丂峴丂丂拞悽偺僞僺僗僩儕乕乬Apocalypse乗栙帵榐乭傊偺椃亙杒偺棔岺朳丒傾乕僗僱僢僩儚乕僋丂妏丂庻巕亜
晅丂丂榐丂丂夛懃丄塣塩嵶懃丄杮帍偺奣梫丄夛崘
僐 儔 儉丂愼怐兛丄僀儕僗偝傫丄側偧傗偟偒丄僀儞僪偺儅僋僪僫儖僪丄傾儞僕僃
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2005乿栚師
姫 摢 尵丂丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俀夞戝夛 in 壂撽 2005 奐嵜丂亙杒偺棔岺朳庡嵣丂妏丂庻巕亜
尋媶曬崘丂丂拞墰傾僕傾偺僋儕儉僝儞愼椏崺拵 Porphyrophora spp. 偺尋媶丂亙僼儔儞僗崙棫壢妛尋媶僙儞僞乕丂僪儈僯僋丒僇儖僪儞亜
夝丂丂愢丂丂僋儕儉僝儞愼椏崺拵偵偮偄偰偺夝愢丂亙僼儔儞僗崙棫壢妛尋媶僙儞僞乕丂僪儈僯僋丒僇儖僪儞亜
尋媶曬崘丂丂杒傾儊儕僇丒杒儓乕儘僢僷偵偍偗傞抧堖椶愼傔丂亙僇儗儞丒僟僀傾僨傿僢僋丒僇僢僙儖儅儞亜
幚慔曬崘丂丂僆乕僗僩儔儕傾屌桳偺怉暔愼椏傪梡偄偨憂嶌妶摦丂亙愼怐壠丂僟僀丒儅僢僋僼傽乕僜儞亜
尋媶曬崘丂丂僒僇僥傿儞僞偐傜摼傜傟傞怓慺偺摿挜偲偦偺愼怓嫇摦丂亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭丒暉杮敽巕丒屆郷桾庽丄妶悈彈巕戝妛丒寬峃惗妶妛晹丂帥揷婱巕亜
尋媶曬崘丂丂僒僇僥傿儞僞怓慺偺帺慠娨尦塼偵傛傞愼怓丂亙妶悈彈巕戝妛丒寬峃惗妶妛晹丂帥揷婱巕亜
尋媶曬崘丂丂奓巼偵娭偡傞僼傿乕儖僪挷嵏偺惉壥丂亙妶悈彈巕戝妛丒寬峃惗妶妛晹丂帥揷婱巕亜
尋媶曬崘丂丂揤慠愼怓偺嶻拝偵尒傞乽偍傕偄乿 丂亙塅搒媨戝妛戝妛堾丒嫵堢妛尋媶壢 抮尨壚巕亜
幚慔曬崘丂丂憪栘婄椏傪巊偭偨宆愼丂亙憪栘岺朳乮憪栘愼尋媶強奰惗岺朳乯嶳嶈榓庽亜
幚慔曬崘丂丂怉暔偺敪峺愼偲偦偙偐傜弌棃傞婄椏偵偮偄偰丂亙NPO傾乕僗僱僢僩儚乕僋丂妏丂庻巕丄郪揷孿巌亜
夝丂丂愢丂丂儅儎丒僽儖乕丄偙偺儐僯乕僋側桳婡婄椏丂亙愼怐尋媶壠乮嵼僌傽僥儅儔)丂帣搱塸梇亜
夝丂丂愢丂丂宆愼傔偵偮偄偰丂亙朳丂怸丂庡嵣丂栴弌彯巕亜
婭丂丂峴丂丂戜榩偱偺戜杒導嶰嫭棔愼愡偵嶲壛偟偰丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂媿揷丂抭亜
夝丂丂愢丂丂壂撽偺愼怐丂亙棶媴戝妛丒嫵堢妛晹丂曅壀丂弤亜
夝丂丂愢丂丂壂撽偺怉暔愼椏偲攠愼嵻偵偮偄偰丂亙棶媴戝妛丒嫵堢妛晹丂曅壀丂弤亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞俀夞戝夛丂奣梫
峴帠儗億乕僩丂朰傟傜傟側偄斾壝椙桳偝傫偺庤巇帠丂亙塅搒媨戝妛丒嫵堢妛晹 嵅乆栘榓栫亜
峴帠儗億乕僩丂愇奯搰偐傜傫岺朳偱偺愼怓幚廗 丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂媿揷丂抭亜
晅丂丂榐丂丂夛懃丄塣塩嵶懃丄杮帍偺奣梫丄夛崘
僐 儔 儉
僒僇僥傿儞僞丄DHA丄崙嵺僀儞僕僑丒僂僅乕僪夛媍丄儅儎僽儖乕偺幚暔偵愙偟偨偙偲丄宆愼傔亙栴弌彯巕亜丄壂撽戝夛偺姶憐亙彫暯宐旤亜丄惗孞傝巺偲奓巼愼亙嶳懞懡塰巕亜丄偐傜傫岺朳傪朘偹偰亙錗
氭巕亜
婡娭帍乽揤慠偺怓亅揤慠愼椏婄椏夛媍曬崘2004乿栚師
姫 摢 尵丂揤慠愼椏婄椏夛媍偺愝棫偵偁偨偭偰丂丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂媿揷丂抭亜
尋媶曬崘丂憪栘愼偺怓嵤揑摿挜丂丂亙憪栘岺朳乮憪栘愼尋媶強奰惗岺朳乯嶳嶈丂榓庽亜
尋媶曬崘丂奓巼偵娭偡傞僼傿乕儖僪儚乕僋偺惉壥丂丂亙妶悈彈巕戝妛丒寬峃惗妶妛晹丂帥揷丂婱巕亜
尋媶曬崘丂棔偺惗梩偵傛傞巼愼傔偵偍偗傞壏搙偺岠壥偵偮偄偰丂丂亙晲屔愳彈巕戝妛丂媿揷丂抭亜
幚慔曬崘丂澍棔傪巊偭偨捑揵棔嶌傝偲敪峺愼丄偦偟偰偡偔傕嶌傝傑偱丂丂亙杒偺棔岺朳庡嵣丂妏丂庻巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍偺戞侾夞戝夛丂奣梫
峴帠儗億乕僩丂尋媶敪昞丂棔丒僋僒僊傪梡偄偨椢怓愼傔
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儚乕僋僔儑僢僾丂對偺埄愼傔丂丂丂亙柤嶃僇儔乕儚乕僋尋媶夛丂榌丂丂愹亜
峴帠儗億乕僩丂僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞乽揤慠愼椏丒婄椏傪巊偆堄媊?楌巎揑宱堒偲枹棃乿亙婰榐丒曇廤丗媿揷亜
峴帠儗億乕僩丂儚乕僋僔儑僢僾丂捴奃廯攠愼偵傛傞巼崻愼丂丂亙憪栘岺朳乮憪栘愼尋媶強奰惗岺朳乯丂嶳嶈丂榓庽
峴帠儗億乕僩丂儚乕僋僔儑僢僾丂對偺埄愼傔丂丂亙杒偺棔岺朳庡嵣丂妏丂庻巕亜
峴帠儗億乕僩丂儚乕僋僔儑僢僾丂係庬椶偺娷棔怉暔偵傛傞扏偒愼傔丂丂亙杒偺棔岺朳庡嵣丂妏丂庻巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞侾夞戝夛偵傛偣偰丂丂亙塅搒媨戝妛戝妛堾嫵堢妛尋媶壢侾擭丂抮尨丂壚巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍 戞侾夞戝夛偵偰丂丂亙岺朳 怸 庡嵣丂栴弌丂彯巕亜
峴帠儗億乕僩丂揤慠愼椏婄椏夛媍戞侾夞戝夛in暉壀傪廔偊偰丂丂亙捗壆嶈棔偄傠偺夛丂廰揷丂榓旤亜
夝丂丂愢丂丂奓巼偵傛傞愼怓曽朄丂丂亙妶悈彈巕戝妛丒寬峃惗妶妛晹丂帥揷丂婱巕亜
憤丂丂愢丂丂棔偺惗梩愼傔偺妶梡丂丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂媿揷丂抭亜
昡丂丂榑丂丂巕偳傕偲揤慠偺怓丂丂亙傾乕僗僱僢僩儚乕僋搶嫗丂郪揷丂孿巌亜
悘丂丂昅丂丂揤慠愼怓偲巇帠偲娐嫬栤戣偺帠丂丂亙揤慠怓岺朳庤愼儊壆庡嵣丂惵栘丂惓柧亜
婭丂丂峴丂丂僄儖丒僒儖僶僪儖偱偺棔偲揤慠怓慺偺崙嵺夛媍丂丂亙晲屔愳彈巕戝妛丒惗妶娐嫬妛晹丂媿揷丂抭亜
晅丂丂榐丂丂夛懃丄塣塩嵶懃丄杮帍偺奣梫丄夛崘